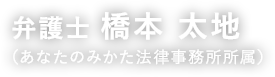2022/12/12 コラム
取調べへの弁護人立会い拒否は法の支配に違反する
日本に法の支配が妥当すべきことに争いはない。これは、専断的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利自由を擁護することを目的とする原理である(『憲法(第7版)』13頁以下(芦部信喜 著、高橋和之 補訂、岩波書店、2019年3月))。なお、類似の概念として法治主義があるが、その由来はともかく、現在は両者はほぼ同じ意味である。
法の支配の派生原理として、法律の留保がある。行政活動については法律の根拠がなければ行うことができないというものである。ここでいう行政活動とは、私人の自由と財産を侵害する行為をいうとされている(侵害留保説。『基本行政法第3版』(Kindle版)75頁以下(中原茂樹、日本評論社、2018年9月))。これは、現在も実務において採用されている立場である。
警察が行政に属することは争いはない。国家公安委員会は内閣総理大臣の所轄の下に置かれ(警察法4条1項)、警察庁は国家公安委員会の下に置かれ(同法15条)、都道府県警は警察庁の所掌事務について警察庁に指揮監督されるからである(同法16条2項)。都道府県警は都道府県に置かれている(同法36条1項)から、やはり行政である。
行政である警察は、取調べを行う。取調べについて、刑事訴訟法は以下の通り定める。
第198条
① 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
③ 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
④ 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
⑤ 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
司法警察職員とは、警察官のことである(同法189条1項「警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。」。なお、他に特別司法警察職員がある。同法190条参照。)。1項を読む限り、被疑者には、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭義務はないし、出頭後何時でも退去する自由もある。逮捕又は勾留されている場合に出頭義務があり退去することができないのかは、解釈上争いがある。いわゆる取調べ受忍義務の問題だが、本コラムでは立ち入らない。
少なくとも、逮捕又は勾留されていない被疑者(以下「在宅事件の被疑者」という。)については、取調べ受忍義務はない。このことは警察実務においてすら争いがないところである。
そして、刑事訴訟法198条を何度読んでも、被疑者の取調べに弁護人が立ち会うことはできないとの記載は、ない。その趣旨に読める記載すらもない。
ならば、被疑者が、自身の取調べにおいて、自身の弁護人を立ち会わせることは、自由である。警察は行政であるから、取調べへの弁護人立会いを拒否するのであれば、それは私人の自由を侵害することになるから、法律の留保に従い、それも実務の採用する侵害留保説により、法律の根拠が必要である。これが、法の支配に基づく論理的帰結である。
にもかかわらず、私が経験してきた限り、警察は、取調べへの弁護人立会いを認めない。そもそも、上述した限り、警察には認める認めないの権限自体がないのだが。
警察は、「取調べへの弁護人立会いの必要性を認めない」と言う。しかし、それは取調べを行う警察にとっての必要であり、取調べを受ける被疑者にとっての必要は考慮されていない。
また警察は、刑事訴訟法47条本文(「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」)を根拠として持ち出すこともあった。しかし、本条は、訴訟に関する書類が公判開廷前に公開されることによって、訴訟関係人の名誉を毀損し公序良俗を害しまたは裁判に対する不当な影響を引き起こすことを防止する趣旨である(最高裁昭和28年7月18日判決最高裁判所刑事判例集7巻7号1547頁)。取調べへの弁護人立会いとはおよそ関連がないことは言うまでもない。
終いには、警察は、取調べへの弁護人立会いを認める法律がない(から取調べへの弁護人立会いは認められない)とまで言う。法律上、取調べを受けるか否かすら、被疑者は自由であるのに、その取調べに弁護人を立ち会わせるには法律上の根拠を、私人である被疑者に求めるのである。法律上の根拠が求められるのは、行政である警察の方であって、論理が逆転している。自由とは国家が与えるものという発想すら垣間見える。
世界に目を向けると、少なくとも先進国では、取調べへの弁護人の立会いは認められている。国際人権(自由権)規約委員会は、日本の第 5 回定期報告書を審査し、2008 年 10 月に以下の総括所見を採択している(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/Concluding_observations_ja.pdf)。
委員会は、警察内部の規則に含まれる、被疑者の取調べ時間についての不十分な 制限、取調べに弁護人が立ち会うことが、真実を明らかにするよう被疑者を説得する という取調べの機能を減殺するとの前提のもと、弁護人の立会いが取調べから排除さ れていること、取調べ中の電子的監視方法が散発的、かつ、選択的に用いられ、被疑 者による自白の記録にしばしば限定されていることを、懸念を持って留意する。委員 会は、また、主として自白に基づく非常に高い有罪率についても、懸念を繰り返し表明する。この懸念は、こうした有罪の宣告に死刑判決も含まれることに関して、さら に深刻なものとなる。
締約国は、虚偽自白を防止し、規約第 14 条に基づく被疑者の権利を確保するために、 被疑者の取調べ時間に対する厳格な時間制限や、これに従わない場合の制裁措置を 規定する法律を採択し、取調べの全過程における録画機器の組織的な使用を確保し、 取調べ中に弁護人が立会う権利を全被疑者に保障しなければならない。締約国は、 また、刑事捜査における警察の役割は、真実を確定することではなく、裁判のため に証拠を収集することであることを認識し、被疑者による黙秘は有罪の根拠とされ ないことを確保し、裁判所に対して、警察における取調べ中になされた自白よりも 現代的な科学的な証拠に依拠することを奨励するべきである。
これに対して、日本政府は、以下の通り回答した(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/foro_jp.pdf)。
2009年5月から、被疑者国選弁護制度の対象事件が死刑、無期又は長期 3年を超える懲役又は禁錮に当たる事件へと拡大されているところであり、こ のように身柄拘束中の被疑者が早期に国選弁護人を選任し、接見の際の助言等 の援助を受ける道が大きく開かれたことや、上記9及び 10 に記載したような取 調べの適正確保方策等が講じられていることから、これらの措置により、取調 べの適正確保が進んでいる。
回答になっていないことは言うまでもない。
法務省は、「我が国の刑事司法について,国内外からの様々なご指摘やご疑問にお答えします。」とし、そのQ7において、「日本では,なぜ被疑者の取調べに弁護人の立会いが認められないのですか。」の項目を置いて回答している。その回答は以下の通りである。
被疑者の取調べは適正に行われなければなりません。
憲法第38条には,「被疑者は,自分にとって不利益な供述を強要されず,強制等による自白や不当に長く抑留・拘禁された後の自白を証拠とすることができない」と定められています。さらに,「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合は,有罪とされない」ことが規定されています。実際,裁判においても,自白が任意になされたものではない疑いがあると判断され,証拠として採用されなかった例もあります。
日本ではまた,制度上,取調べの適正を確保するための様々な方策が採られています。被疑者には,黙秘権や立会人なしに弁護士に接見して助言を受ける権利が認められています。このほかにも,取調べの録音・録画によって,取調べの状況が事後的に検証可能となり,適正を確保することができます。
被疑者の取調べに弁護人が立ち会うことを認めるかについては,刑事法の専門家や法律実務家,有識者などで構成される法制審議会において,約3年間にわたってこれらの問題が議論されました。そこでの議論では,弁護人が立ち会うことを認めた場合,被疑者から十分な供述が得られなくなることで,事案の真相が解明されなくなるなど,取調べの機能を大幅に減退させるおそれが大きく,そのような事態は被害者や事案の真相解明を望む国民の理解を得られないなどの意見が示されたため,弁護人の立会いを導入しないこととされた経緯があります。こうした議論を経て,取調べの適正さを確保する方法の一つとして,取調べの録音・録画制度が導入されました。
要は、被害者や国民の理解が得られないとのことである。本当にそうだろうか。
そもそも、取調べを受けている被疑者が真犯人かどうかはわからないのであるから、真犯人であることを前提とした、被害者の処罰感情や国民の真相解明を望む声を持ち出すのは、前提からして間違っている。法務省自身も指摘している通り、被疑者には黙秘権が認められている。これは日本国憲法38条1項で認められた人権である。しかし、警察から長時間取調べを受ける中、1人で黙秘権を行使するのは容易ではない。黙秘権保障を実効化するためにも弁護人立会いが必要なのである。
警察は、弁護人に見られては困るようなナニカを、取調室の中で行っているに違いない。警察は否定しているが。
以上