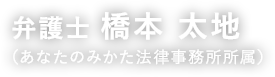2.起訴されてから判決が言い渡されるまで(公判段階)
「保釈」とはどのようなものなのでしょうか。
保釈とは、保釈保証金の納付を条件に、勾留されている被告人を釈放するという手続きをいいます。
保釈されると、被告人は留置場や拘置所から釈放され、自宅などの裁判所によって定められた住居に帰ることができます。
保釈は、一般的には弁護人が裁判所にその請求を行い、これが認められると、保釈保証金を納付することで被告人は釈放されます。
保釈が認められると、裁判の日には、被告人は自宅などから裁判所へ通うことができます。
保釈は、起訴された後にのみ認められます。
被告人にとって、自分が釈放されるかどうかは、肉体的にも精神的にも大きな影響があります。
保釈の実現は、弁護士の行う活動の中でもとても重要なものとなっています。
「保釈」にはどのような種類がありますか。
(1)必要的保釈(権利保釈)
被告人といえども、有罪の判決を受けるまでは無罪の推定を受けます。
一方、長期にわたる身体拘束は、被告人に大きな肉体的・精神的ダメージを与え、その社会的信用も傷つけます。
そこで、保釈の請求があった場合には、例外的な場合を除いて原則保釈を認めることになっています。ここでいう例外的な場合とは以下のような場合をいいます。
① 今回の事件が一定の重大犯罪である場合
② 一定の重大犯罪の前科がある場合
③ 常習犯と認められる場合
④ 証拠隠滅を行う可能性が認められる場合
⑤ 被害者など、証人として出廷するであろう一定の者を脅したりする可能性が認められる場合
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からない場合
実務上、必要的保釈(権利保釈)の請求が却下される理由として最も多いのは、証拠隠滅を行う可能性があるということです。
したがって、権利保釈を獲得するためには、弁護士と相談の上、証拠隠滅の必要性も可能性もないこと,例えば,捜査段階で罪を認めて自白し、共犯者・被害者を含む関係者と内容が一致した供述調書が作成されており、公判で証人尋問等が行われる予定がないことなどなどを主張していく必要があります。
また、弁護士を通じて親族や身元引受人となってもらえる人と連絡をとり、充実した内容の保釈請求書を裁判所に提出することが有効です。
(2)裁量保釈
上述した①ないし⑥に該当する事由があり、必要的保釈が認められない場合でも、裁判所が適当と認めるときは、裁判所の裁量で保釈がなされる可能性があります。
これを裁量保釈といいます。裁量保釈は、保釈の必要性が高く、身元・住所もはっきりしているような場合に認められます。
裁量保釈の決定にあたっては、事件の性質、犯行の態様、犯行に至った事情、被告人の性格・経歴、家族関係・職場環境などが考慮されます。
裁量保釈の決定を得るためには、例えば、被告人が通院を必要とする病気にかかっていることを証明する診断書や、被告人の宣誓書などを提出して、保釈の必要性と相当性を訴えることが考えられます。
また、これ以上会社を休むと解雇される可能性が高いといったことも保釈の必要性を主張する理由となり得ます。
実務上、権利保釈は認められないが裁量保釈は認められるとされる事例は多数あります。
ただ、裁量保釈が認められる条件については、はっきりとした基準があるわけではありません。
保釈について詳しい弁護士に相談して対策を練るのが有効といえます。
(3)義務的保釈
勾留が不当に長くなった場合には保釈を認めなければならないとされています。ただし、この義務的保釈が認められることは実務上まれです。
保釈請求をしてから実際に外に出るまで、
どれくらい時間がかかりますか。
大阪では,保釈を請求した当日には、保釈の決定が出るのが一般的です。
弁護士は、裁判所に保釈請求書を提出した後、裁判官と保釈の許否に関する面談を行います。
この際、ケースによっては、身元引受人らを同伴し、裁判官の説得に努めます。裁判官との保釈面談においては、弁護士が直接口頭で、被告人の身辺状況などを説明することになります。
そして、保釈が認められた場合には、保釈保証金を納付する手続に移ります。
保釈保証金は、弁護士又は法律事務所の職員が、裁判所の担当部署に現金で持参して納付するのが一般的です。
保釈保証金が納付されると、その数時間後に、被告人は釈放されます。被告人の釈放に際しては、裁判所や警察署から家族らに連絡が行くことはありません。
被告人を迎えに行きたい場合は、あらかじめ弁護士と連絡を取り、保釈保証金を納付する日時を確認しておきましょう。
「保釈保証金」とはどのようなものですか。
保釈保証金とは、保釈される条件として、裁判所に納めるお金のことをいいます。
保釈保証金は、被告人が定められた裁判期日に出頭しなかったり、被害者・証人などを脅したりした場合には没収される可能性があります。
しかし、裁判終了までこうした問題がなければ、全額返金されます。
保釈保証金の金額は、事件の重大性や被告人の資力などを考慮して、裁判所が決定します。
被告人が逃亡したり証人を脅したりすることのないよう、充分なプレッシャーとして機能する程度の額を設定する必要があります。
一般的には、100万円~150万円が最低ラインとなっているようです。
もっとも、TVのニュースでも「○○さんの保釈金は××百万円」「○○さんの保釈金は××億円」というのをしばしば耳にするように、事件・被告人によってその額はまちまちです。
事件が重大であるほど、また被告人の資力が高いほど、保釈保証金の金額は高額になる傾向にあります。
なお、保釈保証金の準備が難しい場合、有価証券や被告人以外の者の保釈保証書を提出することでも代替できるとされています。
また、保釈保証金を立て替えてくれる業者も存在します。
保釈された場合、自由に生活できますか。
原則として、「裁判所から定められた一定の条件」を除き、自由に生活することができます。
職場に復帰したり、通学を再開したり、通常の社会生活を送ることができます。
もっとも、「裁判所から定められた一定の条件」に関しては、これを遵守する必要があります。
条件に違反した場合は、納付した保釈保証金が没収される可能性があります。
「裁判所から定められた一定の条件」とは、具体的には、
① 被告人は、○○に居住しなければならない。
② 逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。
③ 海外旅行または3日以上の旅行をする場合には、前もって裁判所の許可を受けなければならない。
④ 事件の関係者に対し、直接又は弁護人以外の者を介して、一切の接触をしてはならない。
などの条件が一般的です。担当の弁護士からよく話を聞いて対応しましょう。
どのような刑事事件が裁判員裁判の対象となりますか?
裁判員裁判の対象事件は,裁判員法の定める重大な犯罪であり,たとえば,殺人罪,強盗致死傷罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪,傷害致死,危険運転致死罪など対象になります。
裁判員裁判の対象事件は,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められており,(1)死刑又は無期の懲役若しくは禁錮にあたる罪にかかる事件,(2)法定合議事件であって,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にかかるものになります。
なお,法定合議事件とは,裁判所法26条2項2号の定める合議体で取り扱わなければならない事件であり,死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪にかかる事件となります(ただし,強盗罪等にかかる事件を除きます)。
これだけでは裁判員裁判の対象事件がよくわからないので,具体例を挙げますと,現住建造物等放火,通貨偽造・同行使,強制性交等致死傷,殺人,身の代金目的略取等,強盗致傷,強盗致死,強盗殺人,傷害致死,危険運転致死などが裁判員裁判の対象事件になります。
刑事裁判の流れを教えて下さい。
刑事裁判は、被告人が起訴状の写しを受け取った後、およそ1か月~2か月後に始まるケースが多いです。
即決裁判の場合は、起訴された日から14日以内に裁判が開かれ、原則としてその日の内に判決が言い渡されます。
裁判所から届いた封筒の中には、弁護人選任に関する書面が同封されている場合があります。
これは、刑事裁判を受けるにあたって、弁護士をどうするかを問う書面です。私選の弁護士を選任する,又はすでに選任している場合は、所定の欄に弁護士の氏名などを記載し、期限までに裁判所に返信しましょう。
国選の弁護人を選任する場合も、所定の欄にチェックを入れ、裁判所に返信する必要があります。
弁護士が決まると、次は、裁判の日程が組まれます。
容疑を否認し、無罪を主張しているような複雑な事件の場合は、裁判の前に争点を整理する手続きが組まれる場合があります。
裁判の日程は、弁護士が付いている場合は、弁護士と裁判所・検察官が協議して、決定することになります。
裁判の当日は、裁判所で弁護士と待ち合わせをし、一緒に法廷に入る場合が多いようです。
逮捕・勾留されている事件では、裁判当日、警察官に連行され、法廷で弁護士と会うことになります。
また、当日の服装についても、裁判官や被害者の方に悪印象を与えないよう、事前に弁護士からアドバイスを受けるようにしましょう。
なお、逮捕・勾留されている事件では、腰縄と手錠をつけられた状態で警察官から連行され、傍聴人が待つ法廷に入るため、傍聴席にいるご家族らに大きな衝撃を与えてしまう場合があります。
この点については無罪推定原則違反とされ最近裁判でも争われ,国際人権の観点からも問題になっています。
実際の法廷でどのような手続きを行い、また判決が言い渡された後にどのような手続きが残っているかは、個々の事件によって異なるため、下記の表を参考にして、担当の弁護士にお尋ねください。
| ①起訴 | |
| ②公判期日の指定 | |
| ③公判期日 | (ⅰ)冒頭手続 人定質問(裁判官による被告人の本人確認) 検察官による起訴状の朗読 裁判官による黙秘権告知 被告人・弁護人の陳述(罪状認否) |
| (ⅱ)証拠調べ手続 | |
| (ⅲ)最終弁論 検察官による論告・求刑 弁護人による弁論 被告人による最終陳述 |
|
| (ⅳ)結審 | |
| ④判決言渡し | |
| ⑤控訴:第1審の判決に不服がある場合上級裁判所に再審理を求める手続 | |
| ⑥上告:控訴審の判決に不服がある場合、さらに上級審に再審理を求める手続 | |
| ⑦判決確定 | |
| ⑧刑の執行 | |
刑事裁判はどれくらい時間がかかりますか。
刑事裁判にかかる時間は、事件によって様々です。即決裁判では、起訴後14日以内に裁判が開かれ、当日中に判決が言い渡されるため、実質1日で裁判が終了します。
通常の簡易な自白事件(争いがなく、証拠関係がシンプルな事件)では、審理に1日(30分~2時間)を要し、約2週間後の判決の日には判決が言い渡されるだけで終了します。
これに対して、事実や証拠を争う事件では、証人尋問や鑑定などを行う必要があるため、裁判が長期化します。
そのため、裁判が終了するまでには、早くて起訴から数か月、遅ければ何年もの期間がかかることがあります。
また、事件(余罪)が複数に及び、再逮捕や追起訴が繰り返されている事件では、証拠関係に争いがなく容疑を認めていたとしても、裁判が終了するまでに1年以上の期間を要する場合があります。
どのようなとき有罪判決が出されるのですか。
刑事裁判において、事件を起訴し、犯罪を証明するのは検察官の責任です。
有罪判決は、検察官によって、被告人が犯罪を犯したことが「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度」に立証された場合に下されます。
「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度」とは、常識的に考えれば有罪と確信できる程度というような意味です。
有罪か無罪かどちらか分からない、9割5分は有罪だが無罪の合理的可能性も捨てきれない、といった場合には、有罪判決を下すことはできません。
無罪推定の原則があるので、刑事裁判の審理は“被告人=無罪”の前提からスタートします。
検察官が、集めた証拠を基に被告人が有罪であることを主張し、証拠調べの結果「合理的な疑い」を超える証明がなされたと裁判官が判断すればようやく“被告人=有罪”となるのです。
被告人側が「自分は無罪だ」と証明しなくてはならないのではなく、被告人を有罪とするために必要なあらゆることを検察官側が証明しなければならないのです。
なお、無罪判決が下される場合には、①検察官が起訴状で主張した事実が証拠上認められない場合と②事実があったとは認められるものの、それが法律上罪にならない場合があります。
とは言っても,現実には有罪推定状態であって,かなり無理のある事実認定により冤罪が多く生み出されています。裁判所は真実をわかってくれるというのは全くの幻想に過ぎないのです。
「無罪推定の原則」とは何ですか。
被疑者・被告人は、有罪の判決が確定するまでは“無罪”と扱われるという原則です。
有罪の判決が確定するまでは、できる限りの自由が尊重され、必要最小限の権利の制約のみが認められます。
被疑者や被告人であっても、あくまで自由(移動する自由、表現する自由など)が認められるのが原則で、犯罪の捜査や出廷の確保のため、どうしても必要な範囲でのみ、例外的に権利の制約が認められます。
TVのニュースなどを見ていると、“逮捕=有罪”のようなイメージを与えかねない報道が多々あります。
しかし法の世界では、有罪の判決が確定する最後の最後まで、被疑者や被告人は“無罪”として扱われるのです。
そして、無罪推定の原則の徹底のために、常に被疑者・被告人の味方として活動するのが、弁護士の重要な役割です。
有罪でも刑務所に行かなくて済む場合とはどのような場合ですか?
懲役刑の有罪判決が下されても、その判決に「執行猶予」が付されれば、ただちに刑務所に入ることはなく、社会の中で日常生活を送りながら更生を図ることができます。
執行猶予とは、罪の重大さ、前科の有無、反省の状況などを考慮して、刑の執行(懲役刑の場合は、刑務所に入ること)を猶予する制度です。
例えば、「懲役3年、執行猶予5年」という判決が下された場合は、すぐに刑務所に入る必要はなく、5年間、その刑の執行が猶予(待ってくれる)されます。
執行猶予の期間中は、基本的には、通常の日常生活を送ることができます。
公務員や一定の専門職など、法律上の制限がある職業を除いては、自由に仕事ができますし、引っ越し、結婚、進学なども自由です。また、海外旅行に関しても、ビザの取得などをクリアすれば、特に制限はありません。
なお、執行猶予の期間中、何も問題を起こさなければ、刑罰は消滅します。
例えば、「懲役3年、執行猶予5年」という判決が下され、判決が確定した日から5年間、特に何も問題を起こさなければ、本件を理由に3年間刑務所に入らなければならない可能性は消滅します。
どうすれば執行猶予付き判決を得ることができますか。
執行猶予が付くためには、法律上まず、①今回の判決が3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金刑を内容とするものであり、②禁錮以上の刑に処された前科がないこと、あるいは、禁錮以上の刑に処されたことがあっても刑の執行が終了してから5年間他の刑を受けていないこと、が必要です。
ただ、この要件を満たせば、必ず執行猶予が付く訳ではありません。執行猶予を付けるかの判断においては、事件の重大性、反省の度合い、被害者との示談が成立しているかどうか、社会の中で更生ができるような家庭環境・職場環境が整っているかなど、様々なことが考慮されます。
この判断は、もっぱら担当する裁判官が抱く心証に委ねられており、法律上特に明確な基準はありません。
そこで、執行猶予付き判決を得るためには、独り善がりな判断で慢心することなく、刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の見通しや自らがとるべき行動について十分に対策を練る必要があります。
特に、被害者がいる事件においては、被害の回復や示談の締結は、裁判において被告人に有利に取り扱われるため、刑事事件に強い弁護士を通じて慰謝の措置をしっかりと講じておく必要があります。